マイホームや投資用不動産を購入した際、本体価格以外にも様々な費用が発生します。
これらの付随費用は確定申告でどのように処理すべきでしょうか?
本記事では、個人の確定申告を念頭に、仲介手数料や登記費用などの付随費用を土地と建物に正しく按分する方法を実例付きで解説します。
将来の譲渡所得税にも影響する重要な知識です。
 ぜいむたん
ぜいむたん


この記事でわかること
- 不動産購入時の付随費用とは何か(個人の確定申告での取扱い)
- 土地と建物に付随費用を按分する方法(確定申告書への記載方法)
- 付随費用の按分計算の具体的手順と実践例
- エクセルを使った自宅でできる按分計算例
- 将来の譲渡所得税を減らすための記録方法と注意点
- 会計士による実践的なワンポイントアドバイス
不動産購入時の付随費用とは
不動産を購入する際には、物件の本体価格以外にも様々な費用が発生します。これらを「付随費用」と呼びます。






| 付随費用の種類 | 説明 | 按分の必要性 |
|---|---|---|
| 不動産仲介手数料 | 物件価格の3~3.3%(+消費税) | 按分必要 |
| 登記費用(登録免許税) | 所有権移転登記などの費用 | 按分必要 |
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額の3~4% | 土地・建物別々に課税 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付する収入印紙 | 按分必要 |
| 固定資産税の精算金 | 売主との日割り計算分 | 別々に精算(明細がなければ按分) |
税務上、これらの付随費用は取得原価に算入できます。
つまり、建物部分に対応する付随費用は減価償却の対象となり、土地部分に対応する付随費用は譲渡所得の計算時に取得費として控除できます。



この記事でも述べた通り、譲渡の際には取得費が大きい方が有利な点がポイントだよ。
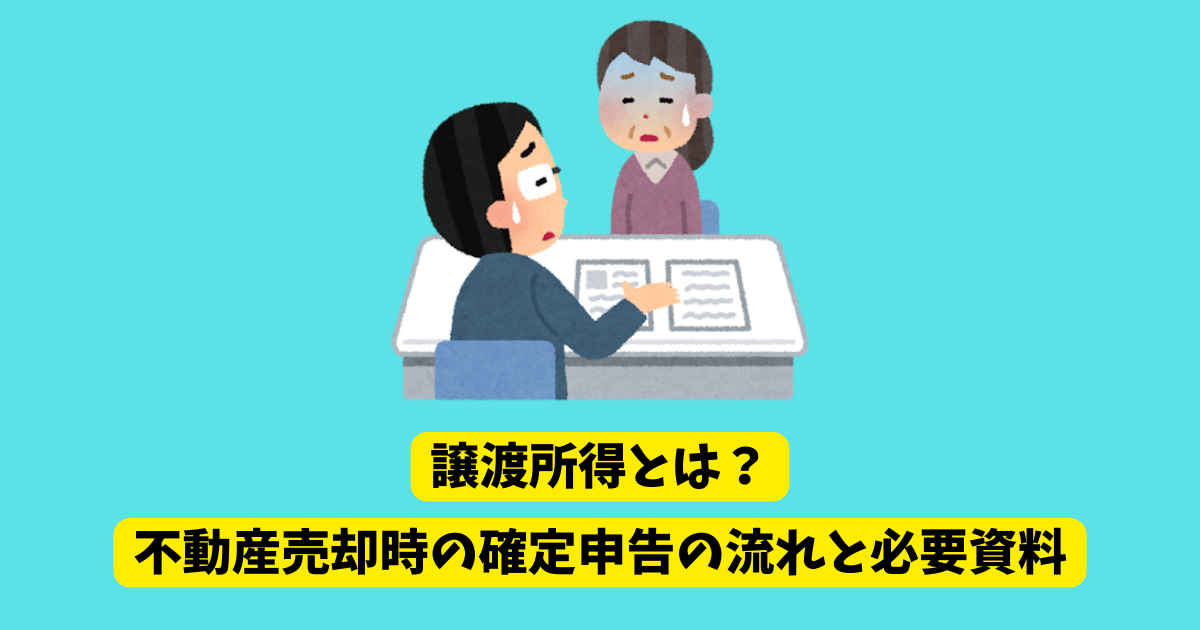
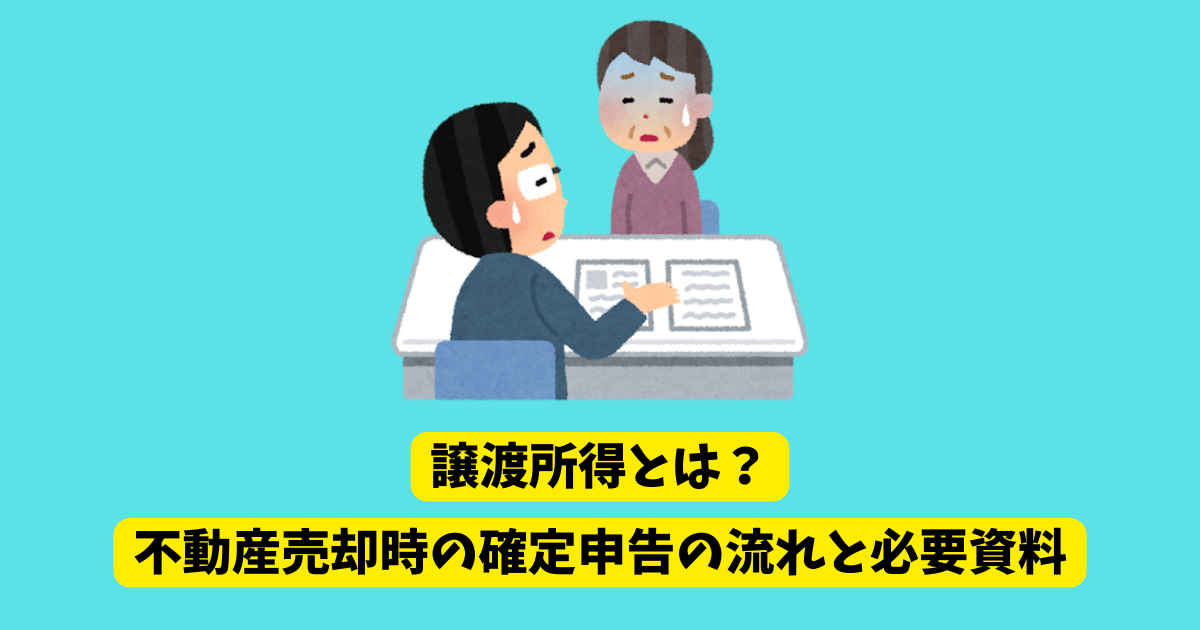
個人の確定申告における付随費用の按分方法
付随費用を処理する方法は、大きく分けて以下の3つがあります。
- 全額を土地の取得原価とする方法
- 全額を建物の取得原価とする方法
- 合理的な基準で土地と建物に按分する方法






なお、付随費用の中には、明確に土地または建物どちらかに関係するものもあります。
例えば、建物の耐震診断費用は建物のみに関係するため、按分せずに建物の取得原価に加算します。
付随費用の按分計算の具体的手順
付随費用を土地と建物に按分するための具体的な手順を見ていきましょう。






- まず、支払った費用が付随費用に該当するか判断する
- 付随費用に該当する場合、土地・建物のどちらに直接関係する費用か確認する
- 共通で発生した費用は、土地と建物の取得価額の比率で按分する
第1ステップでは、支払った費用が税務上の付随費用に該当するかを判断します。
一般的に、不動産の取得に直接要した費用は付随費用となります。
第2ステップでは、その付随費用が土地・建物のどちらに関係するかを確認します。例えば、不動産取得税のように土地分と建物分が明確に区分されているものは、按分せずそれぞれの取得原価に加算します。
第3ステップでは、仲介手数料のように土地と建物に共通して発生した費用を、土地と建物の取得価額の比率で按分します。
確定申告のための計算例:自宅でできるエクセル按分計算
具体的な数値を使って、付随費用の按分計算を見ていきましょう。






| 項目 | 金額 | 比率 |
|---|---|---|
| 土地 | 60,000,000円 | 60% |
| 建物 | 40,000,000円 | 40% |
| 合計 | 100,000,000円 | 100% |
この場合、仲介手数料1,000万円の按分計算は以下のようになります:
- 土地分の付随費用:1,000万円 × 60% = 600万円
- 建物分の付随費用:1,000万円 × 40% = 400万円
つまり、最終的な取得原価は以下のとおりです:
| 項目 | 本体価格 | 付随費用 | 取得原価 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 60,000,000円 | 6,000,000円 | 66,000,000円 |
| 建物 | 40,000,000円 | 4,000,000円 | 44,000,000円 |
| 合計 | 100,000,000円 | 10,000,000円 | 110,000,000円 |
実務では、複数の付随費用が発生することが一般的です。そのような場合は、エクセルなどを使って一括で按分計算すると効率的です。
複数の付随費用がある場合のエクセル計算例






| 付随費用の種類 | 金額 | 土地分(60%) | 建物分(40%) |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 3,300,000円 | 1,980,000円 | 1,320,000円 |
| 登記費用 | 1,500,000円 | 900,000円 | 600,000円 |
| 印紙税 | 60,000円 | 36,000円 | 24,000円 |
| 司法書士報酬 | 250,000円 | 150,000円 | 100,000円 |
| 不動産取得税(土地) | 1,200,000円 | 1,200,000円 | – |
| 不動産取得税(建物) | 800,000円 | – | 800,000円 |
| 合計 | 7,110,000円 | 4,266,000円 | 2,844,000円 |
上記の例では、不動産取得税は土地と建物で別々に課税されるため按分せず、それぞれの取得原価に加算しています。それ以外の費用は土地と建物の価格比率(60:40)で按分しています。
実務上のポイントと注意点






- 按分の基準を統一する:一度選んだ按分方法は継続して適用することが望ましい
- 按分計算の根拠を残す:税務調査に備えて計算過程の資料を保管しておく
- 直接関係する費用は按分しない:明確に土地または建物だけに関連する費用は按分せず直接加算する
- 減価償却への影響を考慮する:建物に按分された付随費用は減価償却の対象となる
マンションの場合の按分計算






マンションの場合、一般的には以下の2つの方法で按分計算を行います:
- 売買契約書に記載されている建物と土地の金額の比率で按分(消費税から建物を逆算)
- 固定資産税評価額の比率で按分
- 建物の標準的な建築価額表による基準で按分
通常は1の方法が用いられますが、売買契約書に金額の内訳が明示されていない場合は2と3の有利選択を行うことが多いです。
よくある質問
























会計士からのワンポイントアドバイス






会計士からの実践的アドバイス
- 電子データと紙の両方で保存
不動産売買契約書、付随費用の領収書、按分計算書はスキャンしてクラウドストレージと紙の両方で保存しましょう。 - 「不動産取得費計算書」を作成する
独自のフォーマットで構いませんので、不動産取得時の価格とすべての付随費用、按分計算を記載した資料を作成し保管しましょう。 - 家族にも保管場所を共有
長期間保管する必要があるため、家族にも資料の保管場所や電子データのアクセス方法を共有しておきましょう。 - リフォーム費用も記録を残す
付随費用だけでなく、その後のリフォーム費用(資本的支出に該当するもの)も取得費に算入できるため、領収書と内容の記録を残しておきましょう。



まとめ:個人の確定申告で押さえるべき付随費用の按分ポイント
個人の確定申告における不動産取得時の付随費用の按分計算についてまとめると、以下のポイントが重要です:
- 付随費用は土地と建物の取得原価に含まれ、将来の確定申告に影響する
- 基本的には「土地と建物の取得価額の比率」で按分するのが確定申告で安全
- マイホームの場合も投資用不動産の場合も、記録は必ず残しておく
- 建物に按分された付随費用は投資用不動産の場合は減価償却の対象となる
- 土地に按分された付随費用は将来の譲渡所得計算時の取得費に算入される
- 按分計算の根拠資料は必ず長期間(10年以上)保管しておく
- 専門家のアドバイスを活用し、将来の確定申告でもスムーズに対応できるよう準備する






不動産の取得費用の計算は個人の確定申告において非常に重要です。特に将来売却する際の譲渡所得税の計算に大きく影響するため、正確な記録と適切な按分計算を心がけましょう。複雑なケースでは、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
関連記事
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務相談は税理士にご相談ください。

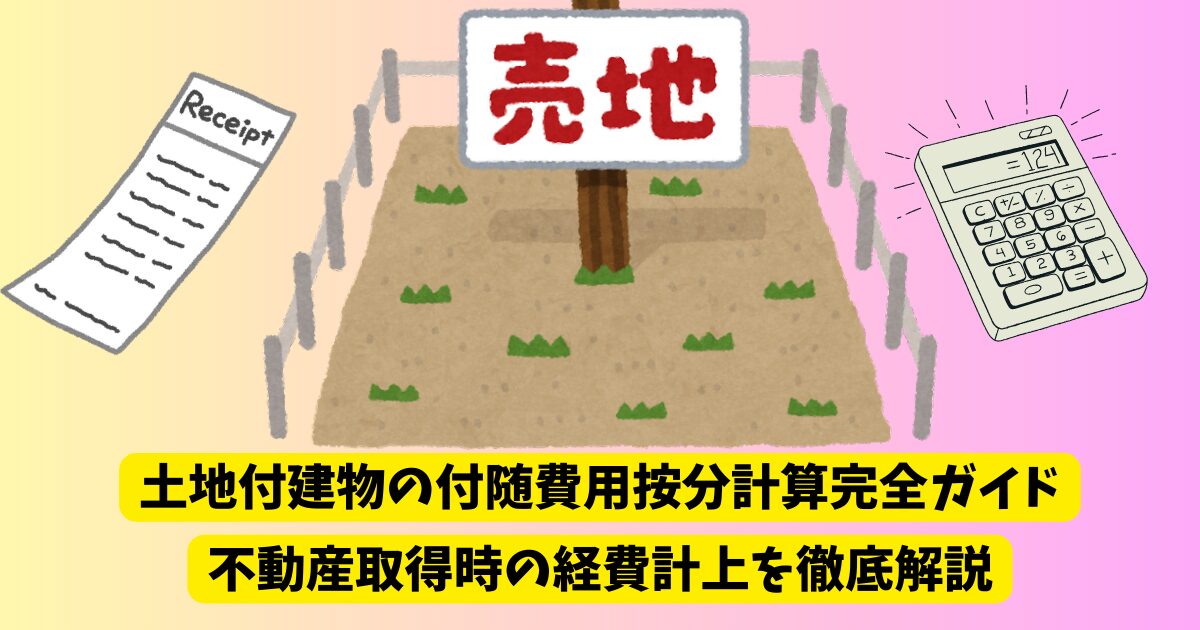
コメント