- 会社経営者に本当に必要な保険の種類と選び方がわかる
- 年代別の最適な保険戦略を立てられるようになる
- 保険を「リスク対策」「資金運用」「節税」の3つの視点から正しく判断できる
- 営業の人に勧められるままに保険に入っていいのだろうか?
- 会社として保険に入るべき?個人として入るべき?どっちが得なの?
- 掛け捨てと積立、どちらの保険が経営者に適しているの?
「この保険で将来の備えができます」「節税にもなりますよ」—こんな営業トークに惹かれて保険に加入したものの、後から「本当に必要だったのか?」と疑問を感じた経験はありませんか?
多くの中小企業経営者が「何となく」「付き合いで」保険に入ってしまい、結果的に損をしているケースが実は少なくないのです。
この記事では、経営者が本当に必要な保険と、その選び方について解説します。
 ぜいむたん
ぜいむたん


保険商品の3つの役割と経営者が知るべき本質
保険には主に3つの役割があります。ほとんどの経営者はこの区別を明確に理解しないまま加入するため、本来の目的とは違う期待をして後悔するケースが少なくありません。まずはこの基本を押さえておきましょう。
- リスクを回避する(保険本来の役割)
- 有利な資金運用をする(金融商品としての保険)
- 税金を安くする(節税商品としての保険)



実務やっとると、多くの経営者が「営業マンとの付き合い」「何となく不安だから」といった理由で保険に加入しとるで!



他の高額な買い物と比べても、保険ほど「なんとなく」で決めてしまうものは珍しいわよね…
1. リスク回避のための保険(保険本来の役割)
保険の基本は「みんなでお金を出し合って、困った人を助ける仕組み」です。つまり、万一の事態に備えてリスクを分散するのが本来の目的です。この目的に沿った保険選びができているかどうかが、まず大切なポイントになります。
| 保険の種類 | 対象となるリスク | 経営者にとっての重要度 |
| 生命保険 | 人の死亡のリスク | ★★★(企業継続に直結) |
| 傷害保険 | 人の傷害のリスク | ★★(収入減少の備え) |
| 年金保険 | 人の長生きのリスク | ★★(老後資金の確保) |
| 火災保険・地震保険 | 火災や地震のリスク | ★★(事業用資産の保護) |






2. 資金運用のための保険(金融商品としての側面)
保険には「長期で固定的な金融商品」という側面もあります。しかし、現在の超低金利環境では、高い手数料を支払って保険という金融商品を購入するメリットはほとんどありません。
「満期金が返ってくる」商品は
手数料・運用コスト・機会損失を考えると
実質的な損失が生じるケースが多い
→掛け捨て保険が合理的な選択に
「掛け捨ては損した気分になる」「お金が戻ってくるとうれしい」という心理を巧みに利用した保険商品が数多く販売されていますが、冷静に計算すると掛け捨て保険の方が合理的なケースがほとんどです。差額は自社内に残して本業での投資や運用に回す方がビジネスとして賢明です。
3. 節税のための保険(税務対策としての側面)
保険は税金対策として活用できる側面もあります。特に中小企業の経営者向けには「逓増定期保険」や「長期平準定期保険」などが節税商品として熱心に勧められることが多いのですが、これらには見落とされがちな問題点も多いのが現実です。
- 「実質返戻率」という計算方法で魅力的に見せるが、他の節税方法と比較すると効率が悪いケースが多い
- 保険料支払いによってキャッシュフローや財務指標が悪化し、銀行融資にも悪影響を及ぼす場合がある
- 現在の低金利環境では、短期で100%を超える返戻率の商品はほぼ存在せず、実質的なコストが発生
- 税制改正によって優遇措置が縮小・廃止されるリスクがある(過去にも何度も見直された歴史あり)






経営者の年代別・最適な保険戦略
経営者の年代や家族構成によって、必要な保険の種類や考え方は大きく変わります。ここでは年代別の最適な保険戦略について、実践的なアドバイスをまとめました。
| 年代 | 優先すべき保険の考え方 | 推奨される対応 |
| 40代前半まで | 家族や事業継続のための リスク対策を最優先 | 掛け捨て保険を中心に検討 差額は事業投資や自社内留保に |
| 40代後半〜50代 | リスク対策に加え 退職金準備も視野に | 掛け捨て+小規模企業共済など 国の制度も積極活用 |
| 50代後半以上 | 相続対策も 重要テーマに | 相続税対策としての生命保険 (死亡保険金の非課税枠活用) |
40代前半までの経営者向け保険戦略
40代前半までの若手経営者の場合、家族のリスク対策と、ご自身の事故・病気リスクへの備えが最優先事項です。この時期は事業拡大フェーズでもあるため、保険料の支出は最小限に抑え、できるだけ事業投資に資金を回すことが合理的です。
- 定期生命保険:家族のための死亡保障(掛け捨て型が最も合理的)
- 就業不能保険・所得補償保険:長期の病気やケガで働けなくなった場合への備え
- 法人契約の生命保険:事業継続や負債返済のための経営者の死亡リスク対策
- 小規模企業共済:国の制度を活用した退職金積立(全額所得控除の節税メリットあり)
この年代では、高額な返戻金付きの養老保険や積立型の保険よりも、必要な保障を低コストで確保できる掛け捨て型保険を選ぶことで、資金効率を高められます。保険料の差額は自社の成長投資や内部留保に回すことで、長期的にはより大きなリターンが期待できるでしょう。
40代後半〜50代の経営者向け保険戦略
40代後半以上になると、リスク対策に加えて、退職金や相続対策も視野に入れた保険設計を検討する時期になります。この年代では複数の目的を同時に達成できる保険選びが重要です。
- 引き続きリスク対策のための掛け捨て型保険(子供の独立などに応じて保障額を見直す)
- 役員退職金の準備のための保険(逓増定期保険などを慎重に検討)
- 事業承継・相続対策のための生命保険(特に後継者が決まっている場合)
- 国の制度を活用した退職金準備(小規模企業共済・iDeCo・企業型確定拠出年金など)
特に資産規模が大きい経営者の場合、相続税対策として生命保険は有効な選択肢となります。被相続人が被保険者かつ保険料負担者となる生命保険契約の死亡保険金は、500万円×法定相続人数分が非課税となるため、計画的な節税効果が期待できます。また、保険金は遺産分割協議の対象外であるため、相続税の納税資金としても利用しやすいメリットがあります。






保険会社選びのポイント – 徹底コスト比較
どんな保険に入るかと同じくらい重要なのが、どの保険会社を選ぶかという点です。同じような保障内容でも、保険会社によって保険料は大きく異なります。一般的には以下のような順番でコストが安くなる傾向があります。
- 全労災・県民共済など各種共済:低コスト運営・非営利組織であり、募集コストが安い
- ネット系生保・外資系生保:営業職員を置かない効率的な運営、バブル期の逆ザヤ負担が少ない
- 国内大手生保:大規模な営業組織の維持コスト、バブル時代の高利回り商品の逆ザヤ負担あり



短期の掛け捨て保険なら保険料の安さを最優。、長期・積立型の保険を検討する場合は、保険会社の財務健全性や支払い能力も重要な確認ポイントや。
保険を活用した実践的な税務戦略
保険を税務戦略に組み込む場合、個人契約と法人契約のどちらが有利かも重要なポイントです。一般的な考え方を整理しましょう。
| 法人契約のメリット | 個人契約のメリット | |
| 生命保険 | ・保険料の1/2が損金算入可能 ・福利厚生として活用できる | ・一般生命保険料控除が適用 ・相続税の非課税枠活用が容易 |
| 損害保険 | ・事業用の保険料は全額損金算入 ・会社の資産保全に直結 | ・地震保険等は所得控除あり ・家計の安定に直結 |






保険料支払いと税務処理の基本
法人で契約する生命保険の税務処理は、保険の種類によって異なります。基本的な考え方を押さえておきましょう。
上記は定期保険の場合の一例です。支払った保険料の1/2が損金(経費)として認められます。他の保険種類や契約内容によっても処理が変わるため注意が必要です。
まとめ:経営者のための保険選びの基本原則
保険は複雑で分かりにくい商品ですが、基本的な原則を理解すれば、あなたに本当に必要な保険を選ぶことができます。以下のポイントを押さえて、賢い保険選びをしましょう。
- 保険の本来の目的は「リスク回避」 – 現在の低金利環境では、掛け捨て型保険が合理的なケースが多い
- 年代によって必要な保険は異なる – 40代前半までは掛け捨て保険中心、40代後半以上は退職金・相続も視野に
- 保険よりも本業での資金運用が原則有利 – 保険料として資金を社外流出させるよりも自社内で運用する方が効率的
- 保険会社によってコストが大きく異なる – 共済や比較的新しい保険会社の方が保険料が安い傾向がある
- 保険の検討前に専門家に相談する – 加入前に税理士や保険の専門家に相談することで後悔を防げる
保険は「何となく」「付き合いで」入るものではなく、自分の会社や家族のリスクを考慮して、必要なものを必要なだけ選ぶことが重要です。特に経営者は、個人としてだけでなく、会社としての保険選びも慎重に行う必要があります。



今日の授業は終わり!また来てや!!

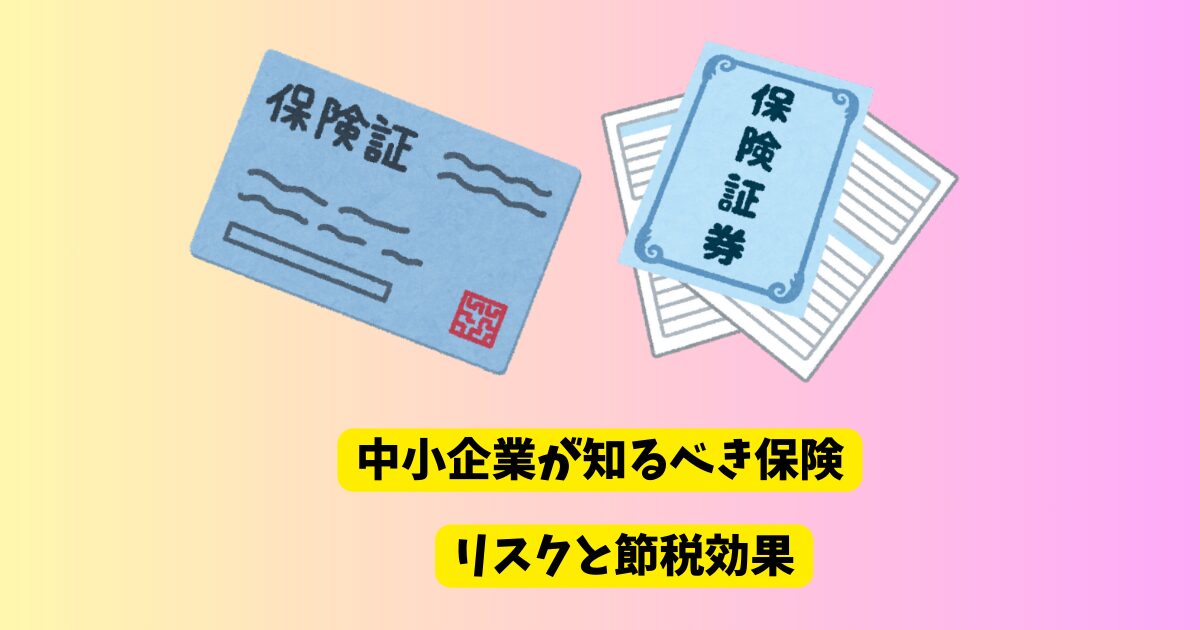
コメント