役員貸付金の基本と利息計算の重要性
中小企業では、会社の資金を役員が一時的に使用し、それを役員貸付金として処理するケースが多く見られます。この処理自体は問題ありませんが、適切な利息を設定していないと、税務調査で思わぬトラブルに発展することがあります。
 ぜいむたん
ぜいむたん


この記事では、役員貸付金の正しい利息計算の方法と、計算を怠った場合のリスクについて解説します。実務で即活用できる計算例も交えながら説明していきます。
この記事でわかること
- 役員貸付金に利息が必要な理由と法的根拠
- 税務調査で指摘されないための適正利率
- 月別残高に基づく正確な利息計算方法
- 役員貸付金と役員借入金の相殺処理の方法
- 実務で使える計算例と仕訳例
役員貸付金に利息が必要な理由とリスク
利息を取らないとどうなるのか?






役員貸付金に利息をつけないリスク
- 役員報酬とみなされるリスク:利息がない場合、貸付金自体が役員報酬と判断され、源泉所得税の納付漏れや不納付加算税が発生
- 贈与とみなされるリスク:利息相当額が役員への贈与と判断され、法人税の損金不算入項目となる可能性
- 同族会社の行為計算否認:税務署が不当な税額減少と判断し、更正処分の対象となる可能性
特に税務調査では、役員への貸付金が長期間にわたる場合や金額が大きい場合に注目されやすくなります。適切な利息計算を行うことで、これらのリスクを回避することができます。
法的根拠と適正利率






「法人が役員に対して金銭を無償で貸し付けた場合には、その法人は、通常、金銭の貸付けに係る利息に相当する経済的利益が役員に供与されたものとして取り扱われます。」
出典: 国税庁 タックスアンサーNo.2606「役員に対する無利息貸付け」
| 項目 | 内容 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 適正利率 | 年0.9%(2023年現在) | 毎年変動する可能性あり |
| 根拠法令 | 所得税法第36条、法人税法第34条 | 経済的利益の供与に関する規定 |
| 適用対象者 | 法人の役員 | 使用人兼務役員も含む |
| 計算時期 | 毎月末または貸付・返済時 | 月次計算が望ましい |
| 申告書への記載 | 勘定科目「受取利息」で計上 | 金額により別表での調整が必要 |
役員貸付金利息の正しい計算方法
基本的な計算式と考え方






役員貸付金利息の基本計算式
月ごとの利息 = 月末貸付金残高 × 年利率(0.9%) ÷ 12ヶ月
年間利息合計 = 各月の利息の合計
【初心者向け解説:月割計算の重要性】
貸付金は月によって金額が変動することが一般的です。年末残高だけで計算すると、実際よりも多く(または少なく)利息を計上することになり、税務上不適切となります。月ごとの残高を基に計算することで、実態に即した適正な利息となります。
役員貸付金と役員借入金の相殺処理






相殺処理の手順
- 月末時点の役員貸付金残高を確認
- 月末時点の役員借入金残高を確認
- 両者を相殺(貸付金−借入金)
- 相殺後の純額がプラスの場合のみ、利息を計算(マイナスの場合は計算不要)
これにより、実質的な貸付額に対してのみ利息が発生するため、より公正な処理となります。
実践!役員貸付金利息の計算例
具体的な計算例






| 月 | 役員貸付金残高 | 役員借入金残高 | 相殺後残高 | 月間利息(0.9%÷12) |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1,000,000円 | 300,000円 | 700,000円 | 525円 |
| 5月 | 1,200,000円 | 300,000円 | 900,000円 | 675円 |
| 6月 | 1,500,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 | 750円 |
| 7月 | 1,300,000円 | 500,000円 | 800,000円 | 600円 |
| 8月 | 1,300,000円 | 700,000円 | 600,000円 | 450円 |
| 9月 | 1,500,000円 | 700,000円 | 800,000円 | 600円 |
| 10月 | 1,800,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 750円 |
| 11月 | 2,000,000円 | 800,000円 | 1,200,000円 | 900円 |
| 12月 | 2,500,000円 | 1,000,000円 | 1,500,000円 | 1,125円 |
| 1月 | 2,300,000円 | 1,000,000円 | 1,300,000円 | 975円 |
| 2月 | 2,100,000円 | 1,200,000円 | 900,000円 | 675円 |
| 3月 | 2,000,000円 | 1,200,000円 | 800,000円 | 600円 |
| 合計 | – | – | – | 8,625円 |
上記の例では、1年間の利息合計は8,625円となります。これを期末に役員に請求するか、給与から天引きするなどの方法で回収します。
仕訳例






利息計上時(決算時):
利息入金時:
または、給与から天引きする場合:
税務調査対策と実務上の注意点
税務調査でよくある指摘事項






- 適正利率の適用:特例基準割合(現在0.9%)未満の利率を適用していないか
- 月次計算の正確性:年末残高だけで計算していないか
- 相殺処理の妥当性:役員貸付金と借入金の相殺が適切に行われているか
- 利息の実際の回収:計上した利息が実際に回収されているか
- 長期未回収の貸付金:実質的に返済の意思がない貸付金がないか
実務上の対応策






役員貸付金の利息対策の手順
役員貸付金の税務対策では、以下の手順に従って処理を行います。初めての方は特に契約書の作成と証憑の保存に注意してください。






- Step 1: 貸付金契約書の作成
金額、期間、利率、返済方法を明記した契約書を作成し、役員と会社双方で保管します。 - Step 2: 毎月の残高管理
役員貸付金と役員借入金の残高を月次で記録し、管理表を作成します。 - Step 3: 利息の計算
月次残高に基づき、年0.9%÷12の利率で利息を計算します。 - Step 4: 利息の仕訳計上
決算時に未収収益と受取利息で仕訳を計上します。 - Step 5: 利息の回収
現金での回収または給与からの天引きにより、実際に利息を回収します。 - Step 6: 証憑の保存
契約書、計算書、入金証明などの証憑を保存します。
特に貸付金契約書の作成と利息の実際の回収については、税務調査で重点的に確認されるポイントです。書面での取り決めと実際の金銭の動きを証明できるようにしておきましょう。不明点がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
会計士からのワンポイントアドバイス






具体的には、役員貸付金が長期間(3年以上)返済されないケースでは、税務調査でより厳しくチェックされます。計画的な返済スケジュールを立て、定期的に返済実績を作ることが重要です。また、利息の計算と回収を忘れずに行いましょう。この点は私のクライアントさんもよく注意されていますね。
税務の現場で役立つ情報は、以下のカテゴリーページからもご覧いただけます。
よくある質問


















まとめ:適切な役員貸付金の管理方法
役員貸付金の利息計算は、税務上のリスクを避けるために非常に重要です。正しい計算方法と処理手順を守ることで、税務調査でも安心して対応できます。
役員貸付金の利息計算 ポイントまとめ
- 適正利率(現在0.9%)で利息を計算する
- 月次の残高に基づいて計算する(年末残高だけでは不適切)
- 役員貸付金と役員借入金は相殺して純額で計算する
- 貸付金契約書を作成し、条件を明確にする
- 計算した利息は実際に回収する
- 証憑類を適切に保管し、税務調査に備える






役員貸付金に関して他にも疑問点がある場合は、コメント欄でお気軽にご質問ください。また、貴社の状況に合わせた具体的なアドバイスが必要な場合は、税理士への個別相談をお勧めします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務アドバイスではありません。実際の税務処理については、最新の税法に基づき、専門家にご相談ください。

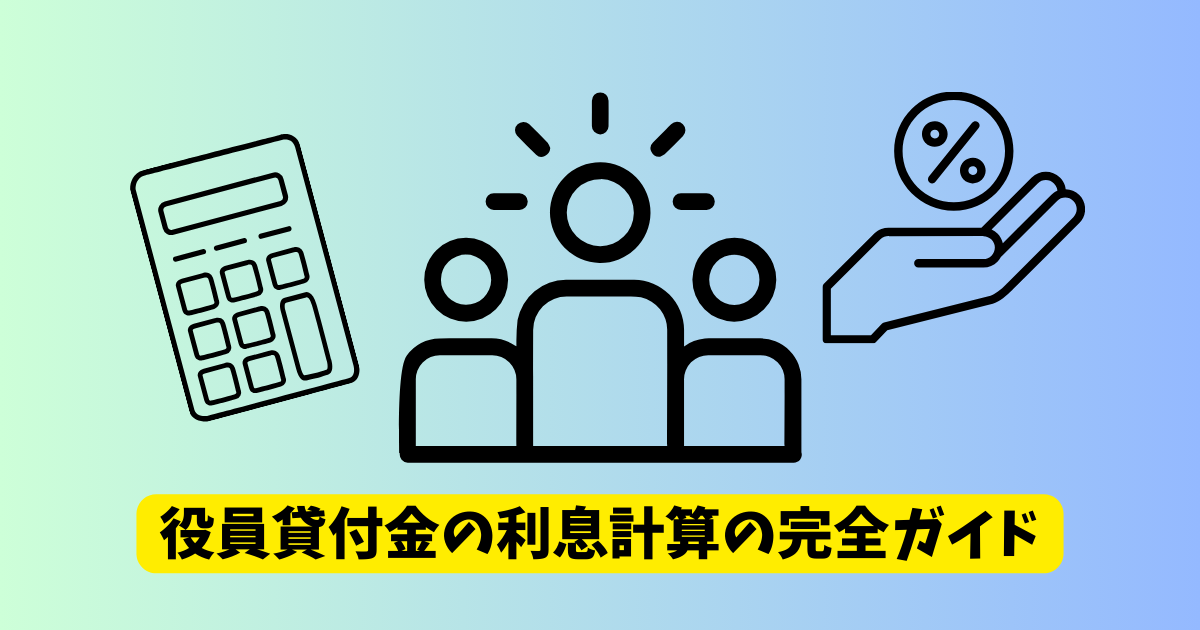
コメント